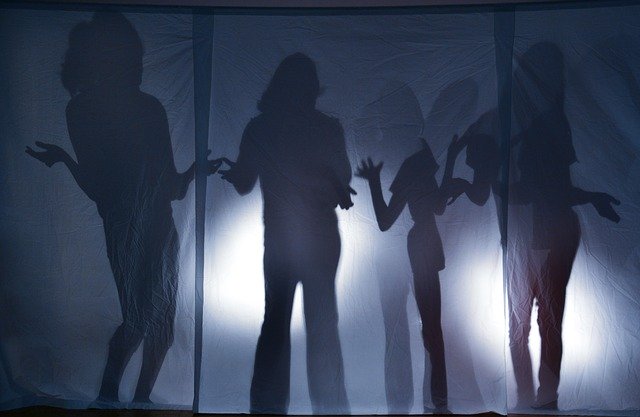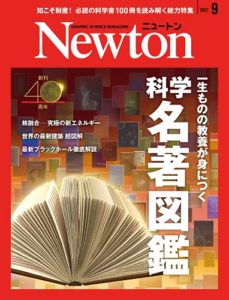「CanSatってなんだろう。誰か教えてくれないかなぁ」
そんな悩みに答えます!
今回はCanSatについて紹介します。CanSatは空き缶サイズの人工衛星づくりの競技です。
なお、僕(@おとな理科のおたれ)の物理学の勉強歴は13年ほど。研究者として生計を立てつつ、サイエンス・エバンジェリストとして科学技術を世間に伝えるための教育活動もしています。こういったバックグラウンドなので、記事の信頼性が担保できるかと思います。
それではいきましょう!
CanSatで学ぶ人工衛星
CanSatとは、缶の形をした人工衛星です。直径は15 cmほどの円柱の形状をしています。缶というには少し大きく4 Lに相当する体積です。主に教育目的に開発しており、日本の高専や大学でもCanSat開発をおこなっています。
人工衛星と同じ機能はあるものの、実際に宇宙まで打ち上げる訳ではないのです。ロケットや気球で上空まで打ち上げて、そこから落とします。競技によって落下中に様々なことをおこないます。例えば、CanSatを落下中に目的地に向けて移動させたり、大気の情報測定をおこなったりといった具合です。
CanSatの面白さは何か

高専や大学ではエンジニア系の部活動がいくつかありますね。例えば、ロボット部や鳥人間なんていうのはかなり有名です。他にもフォーミュラーカーなんてのもありますね。そして、今回紹介するのはCanSatという競技です。
こういったエンジニア系の部活の良いところは、エンジニアリングの基礎が一通り学べることにあるでしょう。機械、電気、システム、物理など様々な能力が必要となるのです。
中でもCanSatは、その競技の特性上、通信技術や計測技術を深く学べる競技になっています。大きさが限定されているので、他の競技に比べると装置にお金がかからないという利点もあるでしょう。
また、社会人の参加も募集しているので、おとな理科を読んでいる僕らの世代でも、まだ参加できるです。
CanSatのイベントはどれほどあるのか

決して知名度が高い競技ではないのです。そのため、年に一度開かれるイベントが主な開催イベントとなっています。世界ではALISS、日本では秋田県で開催される能代宇宙イベント、種子島ロケットコンテストがあります。
ALISSは1999年から年に一度開催されるCanSatイベントですが、残念ながら学生向けのイベントです。一方で、能代宇宙イベント、種子島ロケットコンテストは社会人チームも参加可能になっています。
CanSatの打ち上げは、ロケットや熱気球が用いられています。
チームはまるでベンチャー企業
実際にチームを作るにはどれほどの人数でチームが構成されるのでしょうか。主に以下のような担当に分かれるようです。
- ミッション
- 制御系
- 電源系
- 通信系
- センサ
- アクチュエータ
- ハードウェア
- 地上局
また、資金調達なども含めて以下だ。
- プロジェクトマネジメント
- 財務管理
- 調達
- 文書管理
- 広報
そう、まるでベンチャー企業のようですね。理想的には、それぞれに少人数のグループを作り、開発を進めていくことが理想的です。しかし実際は、通信とセンサ系は同じチームで担当するなどして重複させることがほとんどのようです。
最後に
CanSatに参加している方の話を聞いたことがあります。大学生だったが、目を輝かせながら語ってくれました。
いつかCanSatに参加したいと思って何年も経ってしまいました。Hackthonなどに比べて少しクローズなように感じてしまい、参加できずにいます。社会人で興味ある方がいれば一緒にやりましょう笑
参考文献
この記事は以下の文献を参考にしました。この本、かなり具体的な技術が紹介されています。例えば、エンジニアリングマネージメントとしてVモデルの紹介や、電気回路の基礎、はんだ付けの方法、Xbeeを用いた通信など様々です。CanSatの開発を実際にやっている感覚になれるので面白いですよ。